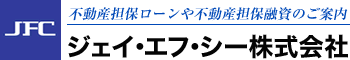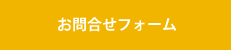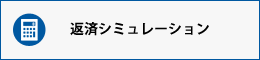共有名義・共有持分と不動産担保ローン(持分融資)について

共有名義・共有持分と不動産担保ローン(持分融資)について
不動産担保ローンでは、借入人(申込者)が所有する不動産を担保として(根)抵当権を設定します。
担保とする不動産の所有者が複数いて、一部の所有者が不動産担保ローンの借入人(申込者)とならない場合はどうなるのか・・・。共有名義の不動産を持つ方は、その活用や資金調達についてお悩みなのではないでしょうか。
共有名義・共有持分と不動産担保ローンについて解説します。
不動産の共有名義・共有持分とは?
不動産の所有権は、1人が100%所有している場合だけではなく、夫婦で50%ずつ、子供も入れて更に複数人で所有するとかケースは様々です。共有名義・共有持分とは、複数の人が1つの不動産を共同で所有することをいいます。
夫婦で不動産を共同購入する場合もありますが、相続が発生したときに相続人が複数で所有するケースも同様です。登記簿(甲区欄)の所有者欄に複数の名前が記載されます。
そして、共有持分とは、共有名義の不動産において各所有者が持つ所有権の割合のことをいいます。
通常、共有持分割合は、不動産の取得に際しての出資額や負担額に応じて決まり、登記簿に所有権割合が登記されます。
共有名義・共有持分の不動産は、売却や担保設定の際に複雑な問題が生じる可能性があるため、所有者間で十分な話し合いと合意が必要です。
共有名義・共有持分で不動産を担保に融資を受けるときの注意点
①共有名義・共有持分をすべて担保に融資を受ける場合
共有持分を担保にする場合、すべての共有者の同意が必要な場合があります。
一般的に金融会社から「物上保証人」「連帯保証人」になることを求められます。
共有持分を担保にした場合、返済が滞り、将来的に抵当権が実行されると、競売により不動産を処分され他の共有者にも大きな影響を及ぼします。
共有者間で十分な話し合いを行い、リスクを理解した上で融資・担保設定を検討することが必要です。
②自分の持分のみを担保に融資を受ける場合
自分の持分のみを担保にする場合、他の共有者に知られず、同意も必要ありません。
他の共有者が物上保証人・連帯保証人になる必要がありません。
但し不動産の登記簿(乙区欄)に自分の持分に対する(根)抵当権の設定登記が行われるため、登記簿を閲覧した時に、持分に担保設定を行っている事実はわかります。
共有持分を担保にする場合、不動産全体を担保にする場合と比べて、金融会社の融資における担保評価額が低くなる場合があります。
自分の持分のみを担保とする場合、金融会社はその持分割合に対して不動産の評価を行います。
不動産の評価には、不動産の流通性も大きな要素となりますが、共有持分だけを売却することは一般的に難しく、買い手が限られるため担保評価額が低くなる可能性があります。
また、他の共有者との関係や将来的な権利調整の可能性があるため高リスク案件となり担保評価額が低くなる場合があります。
自分の持分のみを担保に融資を受けるにあたり、将来、返済が滞った場合のリスクも考慮する必要があります。
抵当権が実行されると、自身の持分が競売にかけられる可能性があります。これは、他の共有者にも影響を与え、共有関係全体を不安定にする可能性があります。
担保評価額が低く、希望通りの融資が受けられないこともあります。
共有持分を担保にする場合は、金融会社と十分な相談を行い、評価額や融資条件を確認することが重要です。
ジェイエフシー(JFC)では、数多くの共有名義・共有持分による不動産担保ローン実績があります。
不動産担保ローン・専業ノンバンクとしての豊富な実績を元に、持分融資のご相談も受け付けていますので、安心してお問い合わせください。